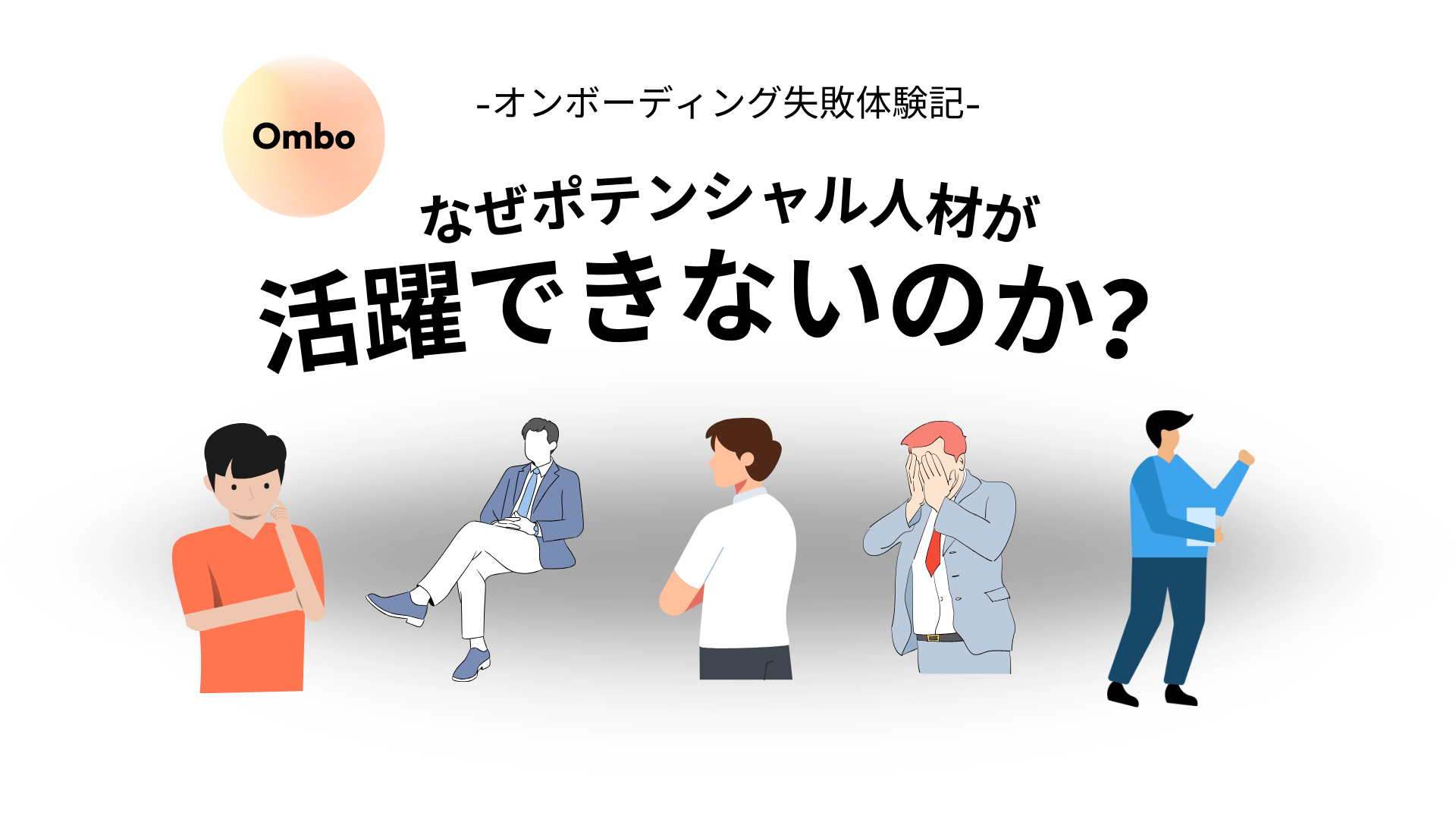なぜポテンシャル人材が活躍できないのか?【オンボーディング失敗体験記】
オンボーディング失敗体験記とは、新入社員の入社オンボーディングにおける一連のプロセスの中で、よくある失敗例を表したコラムです。
そもそもオンボーディングとは、新しく組織に加わった新入社員(新卒・中途の両方を指す)が、早期離職を防ぎながら、企業にとって有用な人材に育成する施策のことをいいます。オンボーディングに取り組むにあたり、このような失敗にならないよう、メソッドとしてご活用ください。
それでは、オンボーディング失敗体験記を見ていきましょう!
オンボーディング失敗体験記
ポテンシャル人材を採用した、とあるIT企業の人事目線での体験記です。
【採用前】
ダイレクトリクルーティング媒体でオファーを出した20代・業界未経験の若手を採用した時の話です。事業計画上、今期数名を採用する計画を引いており、媒体経由である若手の方と面談をしました。
【入社前】
人事の私としては明るく前向きな方だなと思いましたが、一方でやや楽観的すぎるなと気になっておりましたが、社長も「熱意があって、人柄も良いし、頑張ってくれそうだ!」とのことで採用することになりました。
【入社半年後】
努力は人一倍するものの、入社後の立ち上がりに時間がかかり、後から入ってくる社員に、成果でどんどん抜かされている様子でした。最初は前向きに努力しておりましたが、成果に繋がらないことから徐々に元気がなくなっているように見えました。
【入社1年後】
人事の私から社長に相談しても「彼なら大丈夫だよ」と信じて待っているようなスタンス。そんな中で私の嫌な予想が的中し、メンタル不調で会社に来れなくなってしまい、そのまま退社することになってしまいました。ポテンシャルを感じて採用したが、上手く彼を活かすことができず私の中でとても反省している出来事です。これが昨年に起きてしまったポテンシャル人材採用の失敗体験です。
オンボーディング失敗体験記の解説
「ポテンシャル人材」の採用において、注意すべきポイントは、大きく4つあります。
- ポテンシャル人材の定義問題
- 会社側が”勝手に”期待してしまっている - 期待値調整の問題
- 事業がPMFしていない中で(再現性がない状態で)採用を拡大してしまった
- 忠実な実行ができていないポテンシャル人材
解説①ポテンシャル人材の定義問題
そもそも、「ポテンシャル人材」と呼ぶことがありますが、自社におけるポテンシャル人材の定義はなんでしょうか。
リクルート社のサイトでは、以下のように定義されています。
スキルよりも潜在能力を重視して「経験者かどうかは問わない」で募集するのが、ポテンシャル採用になります。(中略)今後の成長を期待できるかどうかが判断基準となります。
採用時は、以下の2点の角度から人材を見ることができます。
ⅰ)性格や思考性がカルチャーフィットしている
ⅱ)スキルセットをどれだけ保有しているか
今回のポテンシャル人材の採用では前者の性格や思考性を重視しています。
ただ、この判断基準が曖昧な場合、見る人により評価が変わってしまったり、入社後フォローの導ち方も不明確なまま走り出すことになってしまいます。
また企業ごとにポテンシャルを発揮してほしい領域が異なってきます。戦略の段階から一緒に考えて欲しいのか、戦略は決まっているから決めたことをやりきって欲しいのか。PDCAでいうところの、「Plan(戦略・企画)」にポテンシャルがあるのか、「Do(実行・実務)」に対してポテンシャルを想定しているのか。
新入社員に対して、何をして欲しいのかを明確に伝えることは重要で、この期待値を伝えられていないまま『新入社員の立ち上がりが、、』と口に出してしまうのは避けたいところです。
解説②会社側が”勝手に”期待してしまっている
「なぜポテンシャル人材が活躍できないのか?」の原因の1つに「期待値調整ができていない」があります。
より厳密にはポテンシャル人材の定義が定まっていないため、採用段階でのミスが原因になるパターンと、ポテンシャルの発揮の方向性が定まっていないことから、入社後フォローミスが原因になるパターンがあります。
いずれにしても人によって見解が分かれるワード(リーダーシップ、コミュニケーション能力、バイタリティなど)は事前の共通認識を取ることが大切です。
解説③事業がPMFしていない中で(再現性がない状態で)採用してしまった
ポテンシャル採用のミスの原因としてあまり注目されない視点ですが、「事業がPMFしていない中で、ポテンシャル人材を採用」することは危険!というのは今回のnoteで最も伝えたい内容です。
PMFとは、プロダクトマーケットフィットのことです。
自社のプロダクト(商品・サービス)が顧客のニーズを満たし、正しい市場に提供されている状態をPMF(Product Market Fit/プロダクトマーケットフィット)といいます。
出所:PMF(プロダクトマーケットフィット)のよくある質問に一問一答 | 株式会社才流
特に事業を興し始めたタイミングで起きてしまう問題ですが、マーケティングと同様に事業の見通しがついていない段階での、ポテンシャル採用は時期尚早と言えます。多くの場合、PMFからポテンシャル人材に任せるということは少ないはずで、一定勝ち筋が見えてきたタイミングの方が良いでしょう。0→1フェーズでともに正解を探しに行きたい場合にも、ポテンシャル人材を採用してしまうと、成果を出せずに苦しんでしまい、早期離職に繋がってしまう可能性が高いです。
解説④忠実な実行ができていないポテンシャル人材
そして、3には当てはまらず、事業自体は順調に伸びているが、ポテンシャル人材が成果を出せていない場合には、オンボーディングに原因がある可能性もあります。
例えば、「めっちゃ頑張ります!」と意気込んでいる新入社員がいたとしても、努力の仕方が間違っているケースがあります。その場合「ただ突っ走る」状態になってしまい、結果として成果に結びつきづらいことが往々にしてあります。
人によって理解のスピードは異なるかもしれませんが、考え方の癖や性格を把握しながら、適切にフォローしていくことがポテンシャル人材の早期立ち上がりに重要です。
ポテンシャル人材と入社オンボーディングで気をつけること
ポテンシャル人材の受け入れにおいて入社後のオンボーディングは特に重要ですので、オンボーディング時に意識すべきことを、3点挙げてみます。
- 期待値調整をすること
- 成長マインドセットをつくってあげる
- 短期のゴールテープを用意して、達成させる
1. 期待値調整をすること
繰り返しですが、期待値が定められないまま、「とりあえずのポテンシャル人材採用」は注意が必要です。
特に、やる気がある若手のポテンシャル人材にとって、努力しても成果が出ない状態や、頑張り方が分からない状態は非常に辛く、結果として離職に繋がるケースはとても不幸ですし、多々見受けられるケースになります。
マネジャーと新入社員との間でのコミュニケーションの中で、
- その事業部での一人前の定義
- やるべき業務の明確化
- いつまでにどのような状態になっていてほしいのか
- 新入社員側からの不安や懸念の洗い出し
- 今後どのようなフォローを取っていくのか
この辺りをしっかりと共有・確認しておくことが重要です。「思ったよりも相手に通じていない」こともあるので、言葉にして伝えていき、双方間ですり合わせを行いましょう。
2. 成長マインドセットをつくってあげる
成長マインドセットとは、人の能力は努力により向上するという考え方で、マインドセットは行動と結果に重要な影響を与える要素です。
https://x.com/Ombo_bs/status/1761863898364531101
成長マインドセットでは、一般的に「7S」を意識すると良いと言われています。ポテンシャル人材の内的キャリアに触れ、本人はどこに意思があるのか?を一緒に見つけ、今の仕事でどうそれを実現するのか?を考えてあげましょう。
「7S」とは、Strategy(戦略)、Structure(組織構造)、System(システム・制度)、Shared value(共通価値観)、Style(社風)、Staff(人材)、Skill(能力)のこと。
3. 短期のゴールテープを用意して、達成させる
新入社員のオンボーディングにおいて、短期で小さい成功体験を積ませる経験は非常に重要です。「3年後にはマネジャーになろう」よりも「1ヶ月後にみんなが営業で使える武器資料を作ってほしい」と伝えた方が、より臨場感を持ったゴールのため、行動に移しやすいです。そして、実績を残せた際には、しっかりとチームで評価することにより、組織に馴染むことができた、役に立つことができたという自己効力感にも繋がります。
ポテンシャル採用するからこそ「脱ポテンシャル」しなければならない
ポテンシャル人材を採用するからこそ、組織はポテンシャルを活かせるような仕組みづくりが必要です。
再現性を持たせた事業になるような努力と、実際に採用ができた際には、上記①〜③のことを意識しながら、皆さんのオンボーディングが順調に進んでいくことを願っております。