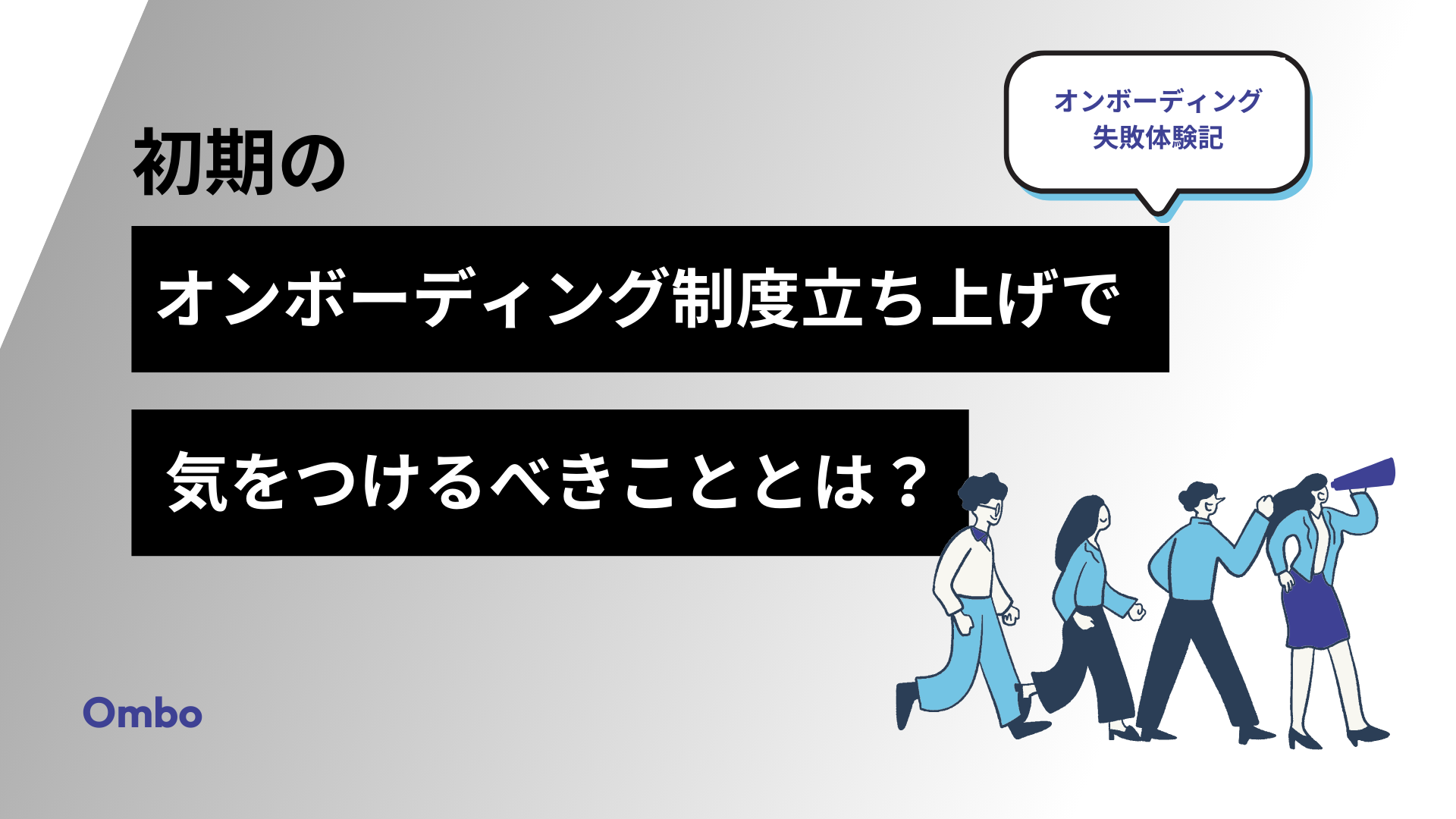初期オンボーディング制度立ち上げで気をつけるべきこと【オンボーディング失敗体験記】
オンボーディング失敗体験記とは、新入社員の入社オンボーディングにおける一連のプロセスの中で、よくある失敗例を表したコラムです。
そもそもオンボーディングとは、新しく組織に加わった新入社員(新卒・中途の両方を指す)が、早期離職を防ぎながら、企業にとって有用な人材に育成する施策のことをいいます。オンボーディングに取り組むにあたり、このような失敗にならないよう、メソッドとしてご活用ください。
それでは、オンボーディング失敗体験記を見ていきましょう!
オンボーディング失敗体験記
あるITベンチャー企業が、事業の拡大とともに採用人数も増え、オンボーディング制度立ち上げへ挑戦する事例です。
第0フェーズ:人の定期採用
- 初期の事業が上手くいき、資金調達にも成功
- 事業の成長とともに人が増える
第1フェーズ:オンボーディングへの意思決定
- 従業員数も20名を超え、毎月新しいメンバーが入社する組織へ
- 同時に、即戦力人材の早期離職や新入社員の成果を出せるまでの期間のばらつきが目立ち始める
- 組織として、オンボーディングに注力することを意思決定。社内先鋭メンバーを集め、オンボーディングチームを組成
第2フェーズ:オンボーディングプログラム作成に着手
- オンボーディングプログラムの作成に着手
- オンボーディングに関する適切な情報の仕入れが難しいことに直面したが、社内メンバーへのヒアリングなどを通し、1ヶ月のオンボーディングプログラムを作成
- 新入社員に対して、活用スタート
第3フェーズ:オンボーディングに問題発生
- 作成したプログラムに沿って実施するものの、オンボーディングの質にかなりのバラつきが出てしまう問題が発生。施策開始から、数ヶ月経った後で判明
- 振り返り(効果検証)ができていないことを課題認識。オンボーディングチームと現場の間に温度感があることを認識。
問題例)現場マネジャーの多忙により、研修がリスケされ、結局実施されていないことが判明
マネジャー: 「全社的なオンボーディングプログラムが重く、現場でやらせたいことができないです…」
問題例)整理する暇なく研修コンテンツが詰まっており、新入社員側で消化不良になっていることが判明
新入社員: 「情報を整理する時間が欲しいです…」
第4フェーズ:改善に着手
- 現場へのヒアリングを実施し、問題・不満を吸い上げた。
- 改めてオンボーディングプログラムを見直し、量を絞り、質を上げるように改良
- オンボーディング運営局側だけが盛り上がるのではなく、組織全体で取り組む意識が醸成されてきた
オンボーディング失敗体験記の解説
今回は、オンボーディングチームをゼロから立ち上げたある企業の失敗談をオンボーディング失敗体験記として描きました。特に注意すべきポイントは、以下4点に整理できます。
解説①事務局だけで盛り上がってしまう問題
オンボーディングプログラム自体には大きな意味はなく、重要なことは「それをどう活用するか」ということです。
初期は、オンボーディングチームで様々な意見を出し合いながら作ります。しかし、気づくと自分たちだけが盛り上がっており、現場サイドは「オンボーディングチームが勝手にやっているな」という感覚になっていることがあります。
オンボーディングは現場の協力ありき、むしろ現場が主役の内容です。いかに組織としてオンボーディングに向かうことができるか、オンボーディングチームはそのモメンタム(勢い)を作ることの方が重要度が高いでしょう。オンボーディングは、プログラムを作ってからが勝負と認識しましょう。
解説②振り返りができていない問題
オンボーディングコンテンツを用意し、スケジュール通り実施はしているものの「それって本当に効果があるの?」と振り返りができていない企業が多々見受けられます。
例えば、1on1施策1つとっても、目的や運用方法、理想の状態などが共有できていないと優先順位が下がったり、属人的なやり方になってしまいます。
そもそもオンボーディングは、業務キャッチアップや会社への順応の仕組み化が目的だったはずです。気づいたらオンボーディング自体が属人的になってしまっては、本末転倒な状況になってしまいます。
各コンテンツに対して、目的・運用方法・ゴールなどを、関わる全員で共通認識を持ちましょう。実施後には、良かった点と改善が必要な点をきちんと振り返ることが大切です。
特に、初期はオンボーディングコンテンツの過不足が見受けられます。あくまで「現場のため」「新入社員のため」ということを忘れずに、手段の目的化が起きないように心がけましょう。
解説③オンボーディングの共通認識が取れていない問題
「オンボーディングとは何か?」の共通認識を取ることが非常に重要です。
ある企業では、「オンボーディング=新入社員を早く組織に馴染ませるためのもの」とだけ共有されていたことがありました。また、ある人は「オンボーディング=早期戦力化」と認識しており、別の人は「会社の人と関係構築をすること」だと認識していました。
共通認識が取れていない場合、例えば「カジュアルランチを実施しよう」という意見に対して「ランチ行くよりも、サービス理解の時間を取ったほうが良い」と、ちぐはぐなコミュニケーションになってしまいます。
一般的にオンボーディングは、仕事ができるように伴走することでもありますし、社員と関係を構築することでもあるので、どちらも間違ってはいません。ただ、情報のインプットの仕方や、前職の経験などを踏まえ、異なる前提で行ってしまうと、どうしても差が出てきてしまいます。いつまでにどういった状態を目指すものなのか、そのために何をするのかといった共通認識を持つことが求められます。
解説④新入社員がお客さまになってしまう問題
新入社員にとってオンボーディングプログラムが用意されていることは一定の安心感につながります。一方で、それがかえって、ネガティブに働いてしまうこともあります。
1日のスケジュールがオンボーディングコンテンツだけで埋まってしまい、「こなすことで精一杯」という状態は危険信号だと言えます。その状態が続くと、「コンテンツに沿って進める”だけ”でOK」となってしまうおそれがあるからです。結果として、受け身状態がスタンダードになってしまう現象です。
これが今回の落とし穴です。
これまでベンチャー企業らしく、主体性を持って進めてきた社員が残ってきたからこそ、「指示前提の動き」は、既存社員が求めていることではありません。
ビジネスサイドのスタンスは、これまで通り主体的に動いてほしい、自分からキャッチアップしてほしいと思っていました。しかし、オンボーディング期間後によって、新入社員と既存社員の間で差が出てしまいました。
オンボーディングプログラム作成で意識すべき3つのこと
様々なハードシップを乗り越え、オンボーディングを軌道に乗せた企業もたくさんあります。最後にオンボーディングで意識すべき3つのアクションをご紹介します。
1. 新入社員へマインドセット研修の時間を用意する
オンボーディングプログラムの一番最初に「マインドセット研修」を用意することです。
内定承諾から入社までの期間が空いていることもあり、改めて自身の入社理由を見つめ直すことで、高いエンゲージメントでオンボーディングに望むことができます。合わせて、新入社員のスタンスを明確にすることで、その後の仕事への取り組みに大きく影響を与えます。
例えば、会社のバリューを新入社員用に置き換え、具体的な仕事のスタンスを組織のチャンネルに投稿してもらうことをおすすめします。既存メンバーは、そのオリジナルな意見やアイデアに対して、反応をしていくことで良いカルチャーを生み出します。
2. 一人前を定義すること
「いつまでにどんな状態になって欲しいのか」という明確なゴールを用意するだけで、インプットの仕方やオンボーディングに望むスタンスが変わります。
「とりあえず先輩社員に業務を教わりながら、任せた仕事をできるようになってほしい」というリクエストは長期雇用前提の旧来の日本企業スタンスそのものです。特に、若手人材は、市場価値が高い人材になる必要がある、いわばキャリアの早期構築願望が高まりつつあります。終身雇用制度の終焉、人生100年時代の背景から、これまでの世代にはない「自分の身は自分で保証する必要がある」という危機感から来ています。
中途入社者の受け入れでは、最初の6ヶ月の壁を超えられるかどうかが一つのハードルです。「一人前とは?」の定義を明確にし、3ヶ月などの短期的なゴールやロードマップを用意することは、新入社員に安心感を与え、キャッチアップの早期化にも繋がります。
3. 組織全体で取り組むこと
最後に、何より重要なのが「オンボーディングは組織全体で取り組む」ということです。
新入社員の受け入れスタンスがなっていないチームでは、お手並み拝見感が出てしまい、新入社員と既存メンバーの間で溝が生まれてしまいます。
例えば、あるマネジャーが、オンボーディング運営局から「これやっておいてください」とカレンダーを確保され、概要を伝えられたとします。もちろん現場マネジャーは他の業務もあり多忙のため、「なぜわざわざこんなことをやらないといけないのか?」「優先的にやりたいことがあるからスキップ」と優先順位が下がってしまうことは、想像に難くありません。
オンボーディングは「やらせる」でも、「やらされる」でもありません。新入社員が早期に組織で活躍し、事業を成長させるために必要な取り組みです。共通認識を持ち、皆で取り組むカルチャーの醸成が非常に重要です。
もちろんこの意識の醸成は、一朝一夕でできるものではなく、何度も働きかけ、仲間を増やしていく地道な取り組みです。しかし、この取り組みこそが強いカルチャーを生み、組織として他社に負けないバリューへと変わります。
組織全体でよりよいオンボーディングを実現するための第一歩を、この記事を読んでいただきました皆さまが、踏み出せることを心より応援しております!