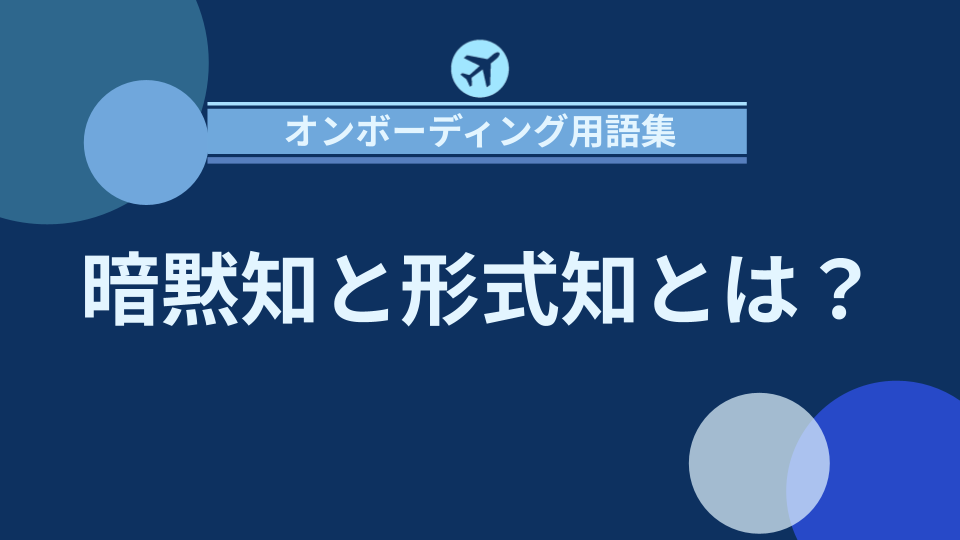暗黙知と形式知とは?知識を共有し組織の成長を加速する方法
企業の成長と競争力強化において「暗黙知と形式知(Tacit & Explicit Knowledge)」の管理と活用は極めて重要です。暗黙知は個人の経験やスキルとして蓄積され、形式知は共有可能な情報として組織に貢献します。本記事では、これらの概念の違いと変換プロセス、具体的な活用方法を詳しく解説し、企業が知識資産を最大限に活かすための方法を紹介します。
暗黙知と形式知とは?
知識には大きく分けて「暗黙知」と「形式知」の2種類があり、これらを適切に活用することが組織の生産性向上に不可欠です。
- 暗黙知(Tacit Knowledge):個人が経験や直感を通じて得た知識で、言葉や文章にしづらいもの。
- 形式知(Explicit Knowledge):文書やデータなど、明確な形で表現・共有できる知識。
暗黙知と形式知の違い
項目 | 暗黙知 | 形式知 |
特徴 | 経験に基づく、主観的 | 文書化・数値化され、客観的 |
伝達手段 | 直接指導、観察、体験 | 書類、データベース、マニュアル |
共有の難易度 | 高い(個人依存が強い) | 低い(誰でも利用可能) |
暗黙知と形式知の変換プロセス(SECIモデル)
野中郁次郎氏が提唱した「SECIモデル」によると、暗黙知と形式知は以下の4つのプロセスで循環し、組織の知識創造を促進します。
- 共同化(Socialization):対話や経験の共有により、暗黙知を他者へ伝える。
- 表出化(Externalization):暗黙知を文章や図表に変換し、形式知化する。
- 結合化(Combination):既存の形式知を組み合わせ、新たな形式知を生み出す。
- 内面化(Internalization):形式知を実践を通じて個人が学び、暗黙知として蓄積する。
暗黙知と形式知の活用方法
1. OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)による暗黙知の共有
先輩社員が直接指導することで、暗黙知を伝承しやすくなります。
2. ナレッジマネジメントシステムの導入
社内Wikiやデータベースを活用し、形式知として知識を蓄積・共有します。
3. ワークショップや勉強会の開催
対話を通じて、暗黙知を表出化し、組織内のナレッジを増やします。
4. マニュアル・業務手順書の整備
業務知識を体系的に記録し、新入社員や他部署への共有を容易にします。
暗黙知と形式知の活用事例
1. 製造業A社の事例
熟練技術者のノウハウを動画マニュアル化し、技術の伝承を実現。
2. IT企業B社の事例
社内Wikiを導入し、暗黙知をリアルタイムで共有し、業務効率化。
3. 医療機関C社の事例
ベテラン医師の診断ノウハウをデータ化し、新人医師の教育に活用。
まとめ
暗黙知と形式知のバランスを取り、適切に変換・活用することで、組織の知識資産を最大化できます。人事担当者や経営層は、自社に合ったナレッジ共有の仕組みを整え、持続可能な成長を実現しましょう。